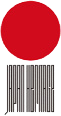公開日 2025年08月26日
伊勢原市内において文化財が集中するエリアの一つに「日向地区」があります。大山詣りの目的地である大山から山を一つ隔てて、構成文化財となっている「霊山寺(現:宝城坊)」が立地している日向山を中心にその麓まで広がっています。この日向地区は、縄文時代から人の居住区域ではあったものの、大山の山麓であることもあり特殊な文化が展開した地域でもあります。ここでは大山詣りにもつながる日向地区の歴史文化についてご紹介します。
1.日向地区の古墳
霊山寺(宝城坊)の創建より遡ること約1世紀、7世紀頃にこの日向地区には数多くの古墳が作られていました。この頃の古墳は、半球状の形をした円墳が狭い範囲にまとまって造られる「群集墳」という形態が多く、日向地区にもかつては多くの古墳が見られたようです。戦中戦後の食糧難の頃にさかんに開墾され、目視できる数は減りましたが、今でも塚状に残る古墳を確認することができます。
一部の古墳では発掘調査が行われており、さまざまな副葬品が出土しています。日向・洗水遺跡では、土地を開墾する際に石室が発見され直刀が出土しました。その鐔(つば)には銀の象嵌(ぞうがん)が施されていました。さらに日向病院建設時に調査された日向・渋田遺跡では、金銅製の鞘飾りが付された飾り大刀が出土しました。これらの副葬品をみると、それぞれに埋葬された人は当時かなりの権力を持った人物であったことがうかがえます。

鎧塚古墳
また、高部屋小学校の北側に広がる鎧塚古墳では、市道1号線の歩道設置工事に際し調査が行われ、横穴式石室から直刀や鉄鏃が見つかっています。この古墳は7世紀に造営されたものであることがわかっていますが、別ページでも紹介している太田道灌にも関係する伝承が残されています。太田道灌の死後、道灌の主君である扇谷上杉定正と、敵対していた山内上杉顕定の両軍が市内の実蒔原で戦となり、多数の死者が出たといいます。最終的に顕定軍は敗走しましたが、そのときの戦死者が葬られたのがこの塚であり、いつしか「鎧塚」と呼ばれるようになったそうです。現在では観音像が彫られた供養塔が建てられており、武者たちの霊を鎮めていると思われます。
2.石雲寺と大友皇子の伝説
日向薬師・宝城坊からさらに北西に進むと、鬱蒼とした深い森と清流豊かな日向川が作り出す日向渓谷が広がります。そんな渓谷のかたわらに、構成文化財の一つである「石雲寺」があります。
石雲寺は、奈良時代初期の養老2年(718)に開創されたといわれる古刹です。寺伝によると、諸国行脚の旅の道中であった華厳妙瑞法師(けごんみょうずいほうし)は、紫雲に導かれるままにこの日向の谷に分け入り寺を建立したといいます。山号を医王山雨降院といい、大山寺と同じく「雨降」の名前を冠しています。

日向字渕ノ上石造五層塔
この寺には、大化の改新の中心人物であった中大兄皇子(後の天智天皇)の息子であり、壬申の乱で敗れた大友皇子に関する伝説があります。大友皇子は壬申の乱の際に近江の山前(やまさき)に逃げ、山中にて自害したとされていますが、異説によると近江から逃げて日向の山中に隠れ住み、その後世間から隠れて一生を送りこの地に葬られたとされています。石雲寺には「真宗明覚大法王」と彫られた大友皇子の位牌が祀られています。さらに、渓谷をやや下りた場所に大友皇子陵といわれる古廟塚があり、大友皇子の墓として石造五層塔が祀られています。この五層塔は14世紀後半の南北朝時代に作られたものであることが判明しており、大友皇子とは時代が合いませんが、貴重な中世の石造物として市の文化財に指定されています。現在は現地にレプリカが置かれ、実物は石雲寺の境内に安置されています。
こうした大友皇子の伝説は全国各地に残されていますが、この地に伝わるということから日向地区の神聖な土地柄が古くから広く認識されていたといえるかもしれません。
3.日向修験と神木のぼり

役行者座像
霊山寺(宝城坊)や石雲寺が創建されたとされる8世紀の前半頃、それまでの自然崇拝を中心としていた大山への信仰が、役行者を開創とする修験道へと変容していきます。修験道を実践する山伏は、山中で厳しい修行をすることにより、山が有する自然の霊力を身に付け、呪術的な力を得ることができるとされています。霊山寺もこの修験道の道場であり、宝城坊本堂の内陣には役行者像が祀られています。
日向修験については、資料が残っていないため詳細は不明ですが、室町時代の文明18年(1468)に、本山派修験の棟梁、聖護院准后道興が霊山寺(当時)へ逗留した記録が残されています。また、戦国時代の永禄12年(1569)には、北条氏と武田氏が争った三増合戦に関連して、相模原市青根にて、北条軍の一員として日向山伏が戦っています。
この日向修験について、当時の山伏が峯入り修行の際に行ったとされる儀式「神木のぼり」が伝統行事として今日に伝わっています。一連の流れを紹介すると、まず椎の木を立ててその周りに結界となる縄を張り道場を設営します。そして法螺貝を吹きながら山伏が入場し、他所からの山伏との問答を行った後、本堂前に立てられた椎の木に登り、祈願を行います。山刀を振るって邪を切り払い、また、護摩を焚き、最後には餅捲きを行い終了となります。現在は地域の有志が保存会を立ち上げ、毎年4月15日に開催される日向薬師春季例大祭において披露しています。

儀式の最後に行われる火渡り
4.銅鐘が語る宝城坊の歴史
日向薬師・宝城坊には本尊の薬師三尊像をはじめ数多くの文化財が残されており、中世以降の歴史資料の中には時の権力者とのつながりが記載されているものがあります。そのような資料の一つに、「銅鐘」があります。

宝城坊の銅鐘
境内東の鐘堂に吊された銅鐘は、銘文によると暦応3年(1340)に鋳造されたものとありますが、さらに読むと天暦6年(952)に村上天皇の発願により鋳造、さらに仁平3年(1153)には院宣(年号からすると鳥羽上皇)により改鋳されたとあります。中世以前の銅鐘は市内にも4口しかなく、さらに天皇の勅願により鋳造、あるいは改鋳されたという記録が残るのはこの宝城坊の鐘のみという点でも重要な資料ですが、この鋳造された時期が宝城坊に残る仏像の製作時期と重なる点が注目されています。本尊の薬師三尊像は10世紀後半、そして本堂に安置されている十二神将像は、調査によると平安末期に製作されたものと考えられています。さらに丈六の薬師如来像、阿弥陀如来像、四天王像は、12世紀から13世紀頃に彫られていると考えられています。この銅鐘の改鋳と仏像の製作時期が重なることは、直接関係しているといえる資料は残念ながらありませんが、少なくともその時期に寺に対し大きな権力が働き、整備が行われたことは間違いありません。
さらに、鎌倉時代の歴史資料である「吾妻鏡」には、幕府の要人が霊山寺に参詣している記載があります。娘の大姫の病の際には家臣を引き連れて源頼朝が、頼朝の死後には鎌倉幕府3代将軍の夫人を伴い北条政子が霊山寺に参詣した記録があります。先の12~13世紀の仏像はこの頃に合致することからも、幕府とのつながり、さらには信仰心の強さを想起させます。
このように、銅鐘に焦点を当てただけでも、その裏にある社会背景や他の資料との結びつきを考えることができ、宝城坊が紡いできた歴史の重みを感じることができます。
5.文化財を未来へ―宝城坊本堂の保存修理―
このように他分野に及ぶ文化財を、後世に継承していくことは容易ではありません。屋外にある資料は自然の影響を受け損傷する可能性があります。また無形の伝統文化はつないでいく人がいなければ継続することが困難となります。こうした文化財を後世に継承していくための「文化財の保存」の取り組みの一つが、宝城坊本堂の保存解体修理です。
現在の境内正面に建てられている宝城坊の本堂は今から約280年前、江戸時代に修理された際の部材で組み上げられています。しかし、茅葺き屋根の葺き替えや部分的な補修を行っていても280年の歳月の間に部材は痛み、内部は虫害の被害に遭うなど危険な状態となっていました。そこで文化庁や県教育委員会をはじめ、社寺建築の専門家等を交えて協議を行い、一度すべての部材を解体して保存修理を行うことになりました。修理にあたっては、「破損した部材であっても、補修や補強等により極力その部材を再用し、取替材は当時の技法・仕様の再現に努める(『文化財建造物保存修理補助事業実務の手引き』)」という方針に基づいて行われ、柱も被害状況から新材に替えざるをえなかった4本を除き、残りは元の部材を補修して復元することになりました。

宝城坊本堂修理作業の様子
この事業の中で、解体するまでわからなかった様々なことが判明しました。現在の本堂の姿になったのが寛保3~延享2年(1743~1745)に行われた大修理の際であること、またその修理の際には従前の万治3年(1660)建立時の部材が再利用されていることがわかりました。さらに、屋根を支える飛檐垂木(ひえんだるき)、枠肘木(わくひじき)等の部材は鎌倉時代に伐採された部材が含まれていることも年代調査により判明しました。解体修理中には床下の発掘調査も行われ、瓦や古銭、仏具と思われる金属製品等が発見されました。
文化財が今の時代まで継承されてきたのは、先人たちの信仰心だけでなく、文化財に対する理解や努力による賜物です。そして、今度は今を生きる我々がそれを引き継ぎ、未来へとつないでいかなければいけません。