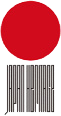公開日 2025年08月26日
大山の麓、昔ながらの里山の景観が広がる比々多地区。大山道がとおり、大山を間近に見上げる立地ということもあり、古代以前から他地域とは異なる生活空間や特殊な信仰が広がっていた場所でもありました。ここでは、先史時代からつながる比々多のヒストリーをご紹介します。
1.大山の麓に広がる縄文・弥生の集落
今から約1万6千年前、氷河時代が終焉を迎え、気候は次第に暖かくなり海水面が上昇をはじめました。これにともない平地では河川が流れ込み、大型動物の狩猟を中心に暮らしていた当時の人々の生活は大きく変わることになります。

三ノ宮・宮ノ前遺跡出土
微隆起線文土器
比々多地区では栗原川や善波川の周辺に集落が広がっていたことが確認されています。比々多神社の境内にあたる三ノ宮・宮ノ前遺跡では、市内最古の土器である微隆起線文土器が発見されているほか、旧石器時代の槍から変化した矢じりが集中して確認されています。縄文時代のはじまりです。さらに、三ノ宮・下谷戸遺跡では立石が並ぶ環状列石が発見されており、大山を臨む祭祀の場であったことが考えられています。大山詣りにつながる信仰の歴史が、縄文時代の時点ですでに芽吹いていたことがうかがわれます。
その後弥生時代に入ると、他の地域と同様、大陸から伝わった米の栽培が始まります。坪ノ内・久門寺遺跡では弥生時代後期の遺跡から炭化した米の塊が発見されました。現在につながるお米の食文化が始まったとみられます。さらに、同遺跡ではグリーン・タフと呼ばれる凝灰岩を素材とする管玉の工房跡が確認されました。またこの工房からは北陸地方、三ノ宮・前畑遺跡では東海地方にルーツをもつ土器が出土しており、この時代に広域の地域間交流があったことを裏付けています。

坪ノ内・久門寺遺跡出土
炭化米
2.古墳の造営
3世紀の中頃から、近畿地方を中心に大規模な古墳の造営がはじまりました。弥生時代までのムラの首長が有力豪族へと変わり、その墓所として古墳が築造されますが、権力の誇示や継承を意図する政治的なモニュメントでもありました。この古墳の造営は、大化の改新で薄葬令が発布される7世紀中頃まで続けられましたが、比々多地区には6世紀後半から7世紀中頃の古墳が数多く分布しています。その多くは小型の円墳が密集する群集墳ですが、比々多神社周辺の丘陵の尾根沿いには首長レベルと想定される古墳が確認されています。
その一つである「登尾山古墳」は、昭和35年に発見され、神奈川県教育委員会と國學院大学により発掘調査が行われました。その結果、横穴式石室の内部から金銀で装飾された大刀、金銅装の馬具、銅鋺、銅鏡、須恵器高坏、土師器坏等が出土しました。このような当時のステータスシンボルともいえる資料がそろって出土した事例は県内唯一です。

登尾山古墳出土
圭頭大刀

らちめん古墳 横穴式石室
また、旧恵泉女学園短期大学の敷地内には、昭和41年に校舎を建設する際に発見された古墳の石室が今でも残されています。江戸時代の新編相模国風土記稿に記載されている地名をとって「らちめん古墳」と名付けられています。この石室からは銀装の大刀、金銅装の馬具、銅鏡、鉄鏃等が出土しました。出土品の荘厳さに加え、確認されている墳丘と周溝から直径40mを測る円墳であることがわかっています。
両古墳とも、6世紀後半から7世紀にかけて相模国を治めていた最高権力者が葬られた墓であると考えられます。現在は里山が広がるのどかな地域ですが、当時の権力者が相模国の中でも特に神聖視した特別な地であったといえます。
3.律令期における「三之宮」
比々多地区における古墳の造営からほどなく、大化元年(645)、中大兄皇子(後の天智天皇)を中心とした勢力により蘇我氏が滅ぼされ(乙巳の変)、大化の改新と呼ばれる政治改革が始まりました。この頃から政治は天皇を中心として皇族によって執り行われるようになり、制度改革の中で統治のしくみや権威付けの在り方が大きく変わりました。その一つが「律令制」です。大宝元年(701)に制定された「大宝律令」により律令国家の第一歩が踏み出されました。この制度に基づき中央集権国家に向けた地方整備が進められ、地方には国・郡・里が置かれ、国は国府、郡は郡家(郡衙)を拠点とする支配体制が定められました。
比々多神社が神社として整えられたのはこの時期と考えられます。前述のとおり以前から多くの古墳が造営され、当時の人々にとっては、通常の居住空間とは分けられた聖地であり、それが次第に神社の成立につながったとも考えられます。この頃にはすでに相模国の国司である布勢朝臣色布知(ふせのあそんしこふち)が社殿を修復し、神前に狛犬を奉納した記録があることからも、国府との直接的な関係もうかがえます。さらに平安時代の天長9年(832)には淳和天皇の詔により「冠大明神」の神号が授けられ、比々多神社は相模の総社として栄えました。


木造こま犬
これ以降、戦国時代の戦火に遭い衰退する時期もありましたが、徳川幕府代々の将軍から社領の寄進を受け、今の比々多神社へとつながっています。
4.孝戒和尚と廻り地蔵信仰
大山や比々多神社への信仰とは別に、江戸時代の中頃から比々多地区において独特な信仰が広がりを見せます。保国寺から始まった廻り地蔵信仰です。

保国寺の大地蔵
当時、保国寺に孝戒という和尚がいました。この頃は富士山の宝永火口の噴火による降灰の被害が甚大で、不況不作が続いたこともあり、多くの子どもが死の危険と隣り合わせの状況に置かれていました。孝戒和尚は子どもに対し深い愛情を持つことで知られており、数多く失われていく幼児の死を悼み、また健全な成長を願って宝暦12年(1762)、丈六の大地蔵尊と百体の小地蔵尊造立の大願を立てました。安永4年(1775)に丈六の地蔵尊は完成しましたが、安永10年(1781)に孝戒和尚は亡くなり、百体の地蔵尊造立は弟子の喝音に引き継がれました。
その後完成した百体の地蔵尊は、旧大住郡内の100ヵ村に分け与えられ、それぞれの集落を戸ごとに一夜の供養を受けながら回る習俗が広まりました。これが「廻り地蔵」のはじまりです。今では主に子どものいる家庭を廻ることが基本で、地蔵尊の泊め方は各地域・各戸さまざまです。巡業の間隔も色々ですが、1年に1回という地域が多いようです。地蔵尊は背負い紐のついた厨子の中に安置されており、この厨子ごと背負われ各家を廻ります。地蔵尊を迎えた家は、この厨子ごと座敷、あるいは床の間に安置し、仏具を飾り食事をお供えします。また、子どもの生まれた家では綿の入った三角の袋(三角袋・三角布団・三角座布団ともいう)を作り、表には願い事、裏には子どもの名前等を書き、厨子の背負い紐の上部にくくりつけます。これを一晩、あるいは数日間で次の家に廻す、ということを地域内で巡業していきます。
現在は少子高齢化の影響もあり、以前と比較すると廻る戸数は減少しているようですが、今でも子どもの健やかな成長を願う気持ちが引き継がれ、比々多地区の三ノ宮を中心に廻り地蔵の文化がつながれています。
※廻り地蔵についての記録映像はこちらからご視聴いただけます。
5.歴史を綴る・地域を綴る―郷土博物館と地域の活動―
比々多地区に暮らす人々は、先史の時代から大山に対して、また自分たちの地域に対して信仰心を持ち、先人たちから受け継いできた歴史や資料を大切にされてきました。すでに明治時代には東京帝室博物館が比々多神社など地元の協力を得て遺跡の発掘調査を実施しています。比々多は遺跡の宝庫として知る人ぞ知る存在だったのです。

三之宮郷土博物館
その思いを形としてつなげてきたものの一つが三之宮郷土博物館です。三之宮郷土博物館は、戦後間もない昭和28年(1953)に、当時の比々多神社宮司であった永井参治氏により建設されました。資料が散逸することを憂い近在の人々の協力を得て整備したものです。当時としては行政以外の博物館は非常に珍しく、全国的にも先駆け的な取組であったといえます。

串橋中世石塔群
[(伝)善波太郎の墓]
さらに、地域も一体となって精力的に文化財の保存や活用に対して各種取組の幅を広げています。串橋にある「(伝)善波太郎の墓」では、市に寄贈された中世の石塔群を、地元有志の保存会が日常的に管理しています。また比々多地区観光振興会では史跡の整備や文化財に関連する自主イベントの開催等、行政とも連携して積極的な企画を実施されています。
「綴る」という言葉には何かをつなげ合わせるという意味や、ある行為や物事を途切れなく続けるという意味があります。比々多地区はまさに歴史・文化財、さらには地域を「綴って」きたと言えるのではないでしょうか。